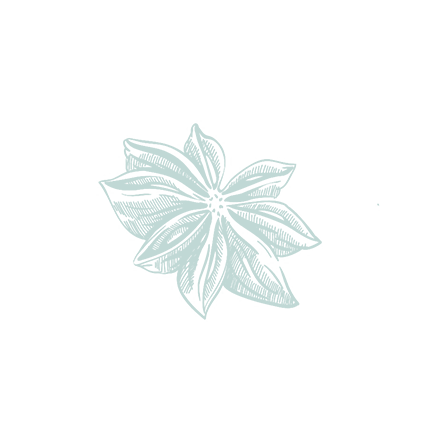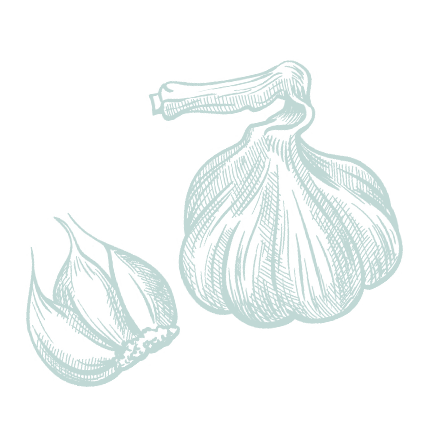BLOG
公式ブログ

繰り返す「口内炎」
口内炎ってなったことがある方が多いですよね。
口内炎とは、口の中や舌にできる炎症のことを言います。
繰り返したり、長引いたり、痛みがあったり、話すのも辛くなるぐらいになる方もいらっしゃいますよね。
原因はさまざまですが、西洋学的には、免疫力の低下、ストレスや栄養不足、ベーチェット病や膠原病、虫歯や入れ歯の不具合、口腔内の乾燥や損傷、ウイルスや細菌の感染によるもの、アレルギー反応による炎症、喫煙の習慣、癌などが原因と考えられています。
殆どの場合は7日から14日もすれば治るものが多いですが、何度も繰り返したり、なかなか治らない場合はお医者さんに相談するようにしましょう。
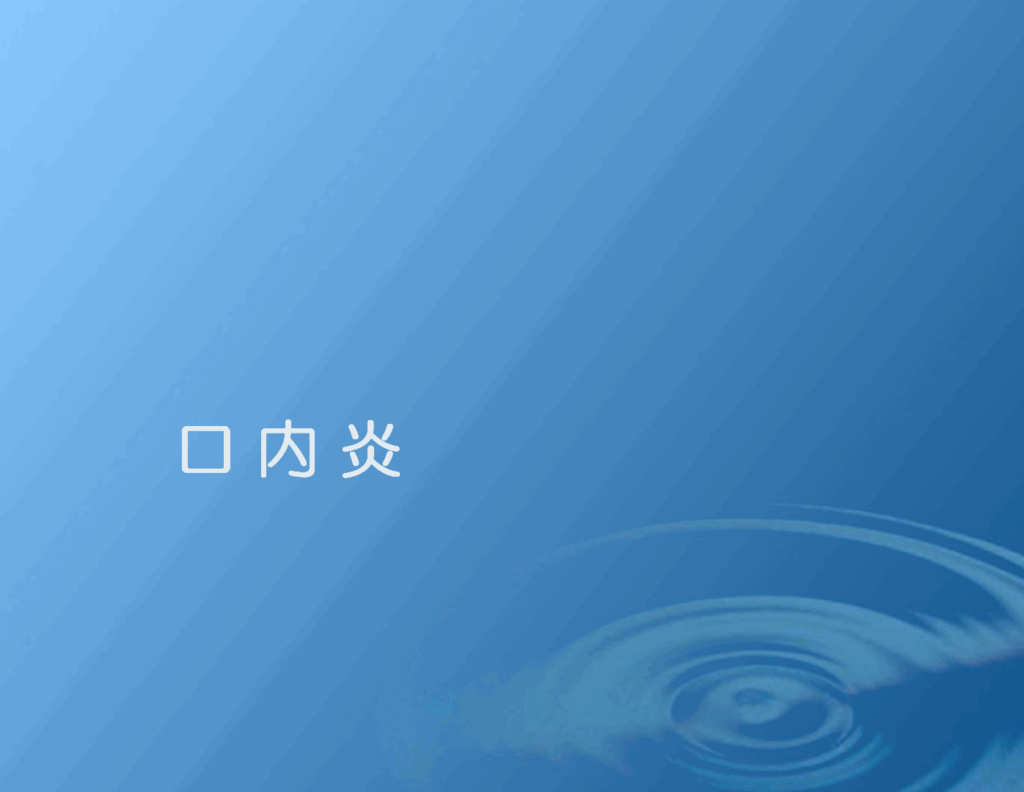
口内炎を中医学で見ると?
「 口 」 のトラブルを中医学では、 「 脾 」 との関連性で考え、 「 舌 」 は 「 心 」 との関連性で考えます。
「 脾 」とは胃腸などの消化器系を指し、 「 心 」 とは心臓を指しています。
さらに 「 脾 」 は 「 胃 」 と繋がっており、 「 心 」 は 「 小腸 」 と繋がっています。ですので、中医学で口内炎を考えるときには、胃腸系と、心のトラブルを前提に考えていきます。
炎症を中医学では 「 火 」 や 「 熱 」 の問題と考えますので、口内炎の原因は、何らかの理由で 「 脾胃(消化器系全般) 」 もしくは 「 心 」 に熱がこもってしまった状態として考えます。
口内炎のタイプは?
口内炎のタイプは 「 実熱 」 と 「 虚熱 」 の2つのタイプに分けられます。
◇実熱タイプ◇
実熱タイプの口内炎は炎症が激しく、痛みも激しいのが特徴。
また急になって2、3日で治まるというのもこのタイプによく見られます。
辛いものや味の濃いもの、熱いものなどの食べ過ぎ、お酒や甘いもの、脂っこいものの食べ過ぎ、全般的に食べすぎると脾胃に熱がこもってしまいます。そのほか、脾胃がもともと弱いことによって、未消化物が残り、それに熱がこもってしまったことも考えられます。
「 脾胃(胃腸系) 」 に熱がこもってしまう一番の原因は食べ物です。
ですので、食べ物を選ぶことが大切になります。
上記のような熱の原因になるものは避けて、潤いがあるもの、熱をとる力があるものを選んで食べるようにすることで、胃腸系の熱を除去することが出来ます。漢方薬を選ぶ場合も同じく、余分な熱を冷ます漢方を選んでいきます。
もう一つの、 「 心 」 に熱が溜まる原因の一番大きなものは、 「 ストレス 」 です。
ストレスは体内のエネルギーである 「 気 」 の巡りを悪くします。悪くなった流れは、詰まったポンプを想像するとわかりやすいかと思いますが、負荷がかかり、熱を発生します。
発生した熱は、その特性により、上へ上へと昇り、体の上部に症状がでやすくなります。例えば、目が血走ったり、カーっとなったり、そして “口内炎” などです。
その他に、ストレスに関連して発生する熱は 「 感情 」 です。
中でも 「 怒り 」 という感情は熱に変わりやすいとされています。ストレスの熱の場合も、食物の熱と同じく 「 熱を冷ます食材や漢方 」 使って対処します。食物や感情、ストレスなど、これらの外的要因によってもたらせた過剰な熱を中医学では 「 実熱(じつねつ) 」 といいます。
~実熱(外的要因による熱)に対する食材~
トマト、きゅうり、冬瓜、苦瓜、大根、豆腐、レタス、ほうれん草、青梗菜、菜の花、水菜、セロリ、セリ、菊花、ゴボウ、レンコン、たけのこ、蒟蒻、もやし、いちご、バナナ、スイカ、キウイ、柿、ビワ、グレープフルーツ、オレンジなど。
よく使われる漢方薬
五涼華・涼解楽・清営顆粒・加味逍遥散・温胆湯など
◇虚熱タイプ◇
虚熱タイプの口内炎は、サイズが小さめで繰り返す慢性的なものが多いのが特徴です。
もう一つの熱に、体内の寒熱のバランスが崩れたことによる「 熱 」というものもあります。人の体は温めるための「 熱 」と、それを抑制する「 水(潤い、津液といいます) 」がちょうど同じ量であることで寒熱のバランスが取れている状態になります。もし水が少ないと熱が相対的に過剰になってしまします。これを先ほどの「 実熱 」に対して「 虚熱(きょねつ) 」と呼んでいます。このような場合は、熱を冷ますよりは潤いを補う食材や漢方を使って対策します。
~虚熱(潤い不足による相対的な熱)に対する食材~
白菜、ゆり根、山芋、人参、アスパラ、クコの実、きくらげ、イカ、ナマコ、豚肉、豆乳、梨、トマト、レンコン、白キクラゲ、アワビ、白ごま、黒ごま、レモン、あさり、鴨肉、豆腐、きゅうり、すいかなど
よく使われる漢方薬
紅サージ・艶麗丹・瀉火補腎丸など
“ 実熱タイプ ”の口内炎の特徴は、サイズ大きめで、強い痛みを伴う潰瘍で、周囲は赤く腫れている。話したり、食事をしたりすると痛みが増します。喉や口が乾燥したり、時には発熱することもあります。
脾胃(胃腸系)に熱がこもっている場合は、食欲が亢進したり、減退したりします。酸っぱい酸が上がってきたり、口臭があることもあります。口の周りにニキビが出たり、唇が赤くなったり、口角が切れることもあります。舌は紅くなり、苔は黄色くなっている時もあります。
“ 虚熱タイプ ”の口内炎では、サイズは小さめで、表目は白くなることもあります。口内炎の周囲は余り赤く腫れがありません。痛みが少ないことの方が多くありますが、繰り返しやすいです。
実熱タイプに対して、胃腸症状が少ない、またはないのも特徴です。口の乾燥や喉の乾燥があり、手足のほてりや肌や髪の乾燥なども見られることもあります。舌は紅く、表目にひび割れが見えることもあります。苔は無い場合、あっても乾燥している場合が多く見られます。
◎実熱タイプは、普段健康な人に起こりやすく、症状は強く出ませんが、治りも早いというのが特徴です。
◎虚熱タイプは、長い間病気をしていたり、体力が落ちている場合に起きやすい口内炎で、症状は強くでませんが、治りにくく、繰り返しやすいという特徴があります。
~口内炎の対策~
どちらも日常的な対策としては、口腔内をきれいに・清潔に保つことと、辛いもの、味の濃いもの、脂っこいものを摂り過ぎないことが大切です。お酒は熱の原因となるので控えめにするといいでしょう。タバコは熱そのものなので、避けてください。
その他では、コーヒーも熱の原因になるので控えめにしましょう。緑茶は熱をさまし殺菌作用もあるので、緑茶の方がいいかもしれません。
食事の基本は、葉野菜たっぷりの和食を中心にするのがおすすめです。
ストレスが原因の実熱タイプの口内炎は、ストレスを発散しましょう。
潤い不足が原因の虚熱は、潤いの源、「腎」を元気にすることが大切になります。歩くことも腎を強化してくれますよ。
そして、どちらのタイプとも、睡眠をしっかりとることも大切になります。